
トラックドライバーに興味を持った方・現在トラックドライバーでより良い運送会社への転職を考えている方は「トラックドライバーのミカタ」がオススメ!。完全無料の「カンタン20秒検索」で、あなたの町の最高待遇求人をチェックしよう!
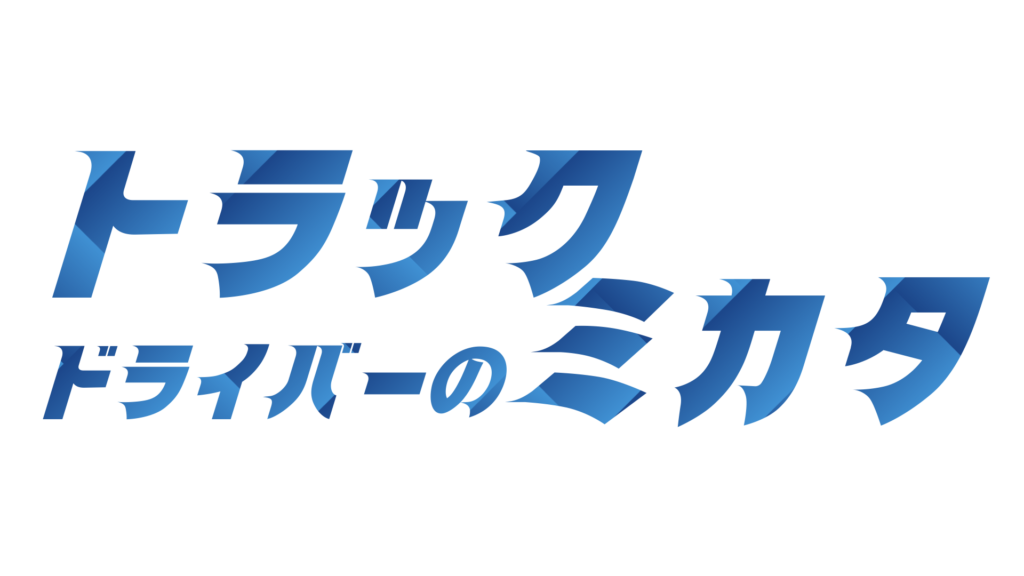

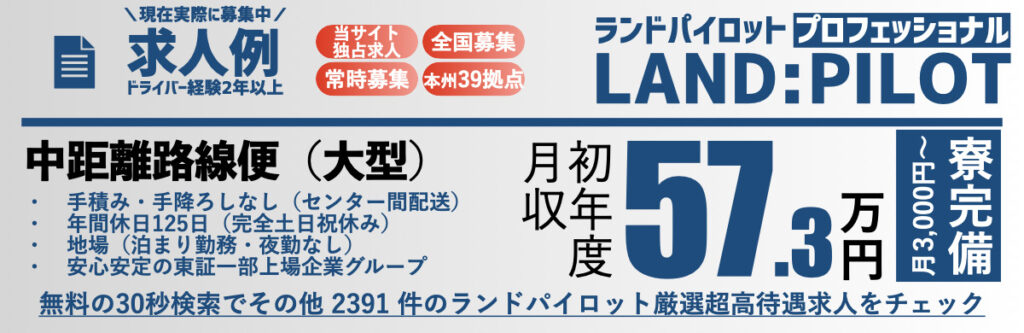
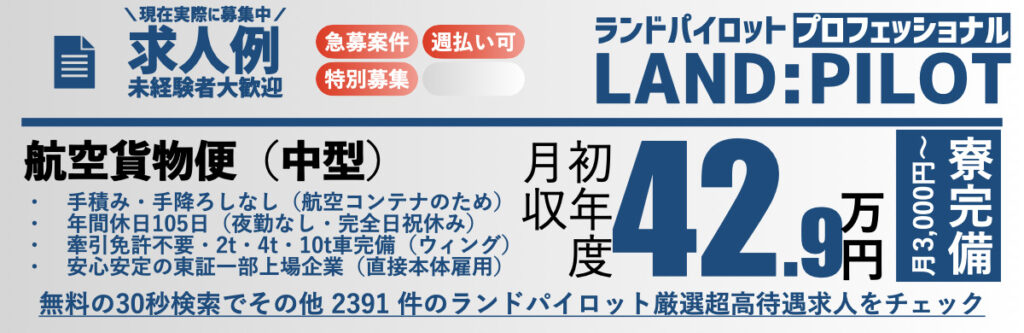
一般的にトラックドライバーの収入は、トラックの大きさや走行距離に応じて変化します。大きかったり、長かったりすれば、仕事に幅が出て、その分給料は増えていきます。
もちろん大型免許を取得すれば、年収が上がることになるのですが、大型免許取得は決して簡単なわけではありません。取得費用も小型・中型に比べると高くなっています。
今回は、大型免許の取得に給付される助成金について解説していきたいと思います。
助成金を活用することで、大型免許取得を安く済ませましょう。
一般的に大型免許を取得するには
まずは、大型免許の取得までの流れや必要な資格、費用について解説していきます。
大型免許取得までの流れ

大型免許の受験に必要な資格・要件
年齢:満21歳以上
資格:普通免許・準中型免許・中型免許・大型特殊免許の取得から3年以上経過
視力:左右それぞれ0.5以上、両目で0.8以上(矯正してもよい)
深視力:三棹法での検査平均の誤差が2cm以内
聴力:10m離れた状態で90dBの警音器が聞こえること (補聴器使用可)
色彩識別:赤色、青色、黄色の区別が可能
大型免許についてはこちらで詳しく解説しているので是非参考にしてみて下さい!
直接試験場に行き一発試験を受ける
教習所に通うことなく直接試験を受けるのが、一発試験です。
メリットとして、教習所に通うのと比べて費用が抑えられるという点が挙げられます。ですが、試験は何日かに渡って行われるので気を付けて下さい。
一発試験の免許取得までの流れ
まず、視力検査などの適正試験を受け、合格したら次に場内試験を受けます。
ここでは、指示された速度で走行できるかなど基礎的な運転ができるのか、さらにはクランクやS字で高度な運転ができるのかが試されます。
これに合格すると仮免許を取得でき、次のステップである路上での練習ができるようになります。
路上での練習は、「大型車で過去3ヶ月以内に5日以上」「有資格者が同乗していること」といった決まりを守りつつやらなければなりません。
有資格者のみならず、車両も自分で準備する必要がありますが、教習所によっては有料で路上練習を行っているところもあるので、確認してみて下さい。
路上練習が終わるとついに、本試験が受けられます。本試験では、場内試験・路上試験の順で行われ、これに合格し、講習を受けるとついに大型免許が取得できます。
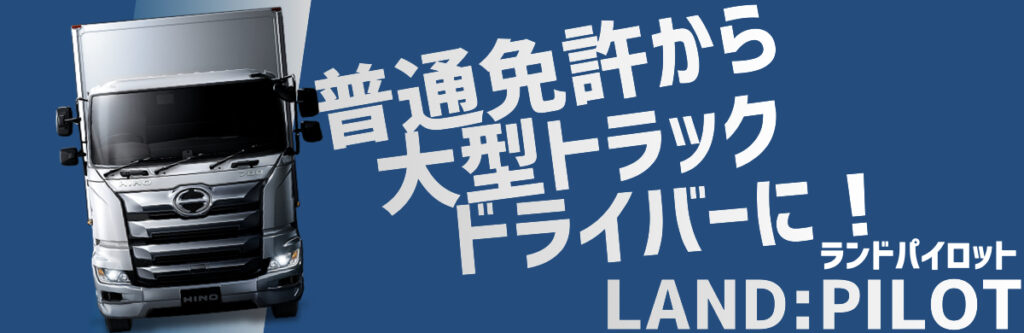
教習所に通うことで免許を取得する
教習所への通いで大型免許を取得するとき、その時点で持っている免許の種類に応じて教習の時間が違います。主な2種類を紹介していきます。
また、教習所についてはこちらで詳しく解説しているのでご参考頂ければと思います!
既に普通自動車免許を取得している
場内教習の第一段階では12時間かかります。その後修了検定に合格し、仮免取得をすると路上教習をおこなう第二段階に進みます。
第二段階では18時間かかります。第二段階終了後には、卒業検定があり、合格すると卒業証明書がもらえます。
この卒業証明書で試験が受けられ、適性検査に合格すると免許が取得できます。
また、別で学科教習が1時間あります。
既に中型免許を取得している
普通免許と順序は同じですが、第一段階で5時間、第二段階で9時間と期間が半分ほどになります。さらに、かかる費用も安くなります。
中型免許についてはこちらで詳しく解説しているので是非参考にしてみて下さい!
大型免許の取得に必要な費用

大型免許の取得に必要な費用はどれくらいなのでしょうか?先ほど解説した、一発試験と教習所通学で費用は異なるので、ひとつずつ説明していきます。
一発試験
一発試験は、費用はおよそ4万円となっており、教習所と比べて格段に安く済ませることができます。さらに、教習にかかる時間がないので、時間も節約することができます。
仮免許取得から5日以上の練習をしなければなりませんが、それでも教習所通学の半分以下の時間で免許取得が可能となっています。
しかし短所もあります。のちに出てくる合格率・難易度の話では、一発試験は合格率が非常に低く、本当に一発で合格できる人はほとんどいないと言われています。
そうして繰り返し受験してしまうと、結局は教習所通学の出費と同じになってしまうことも稀ではありません。
教習所に行く
教習所では、およそ20〜50万円ほどかかります。価格が30万円分も差があるのは、現在持っている免許が何なのかによって値段が異なるからです。
普通免許を持っているならば、およそ35~50万円、中型免許では、およそ20~28万円と普通自動車免許と比べるとかなり安く済ませられます。これは、教習の時間が半分となるので、それに伴って費用もかわっているからです。
教習所へ行くことで免許を取得する方法は、通学と合宿の2つあります。
通学は自分の好きなペースで通うことができますが、その分時間が増えてしまいます。
合宿は、連日集中的に教習を受けなければならないので、短期集中で免許が取得できます。
普通免許を持っていればおよそ2週間、中型免許ではおよそ1週間で大型免許が取得可能となっています。
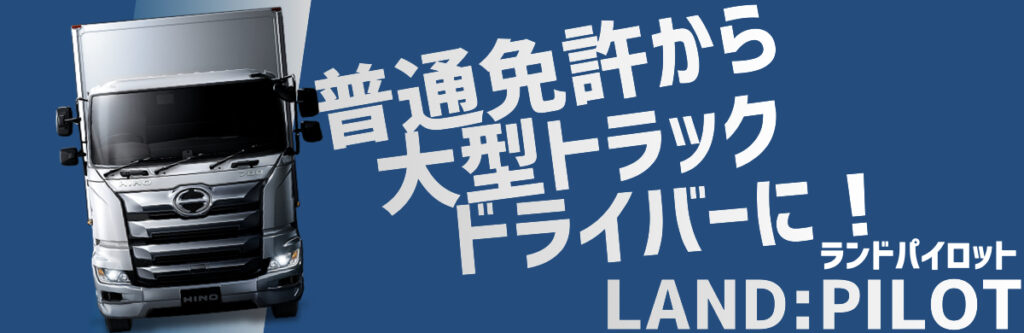
「教育訓練給付制度」を利用する場合
そもそも教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
教育訓練給付制度は、厚生労働省の雇用に関する助成金で、雇用保険の給付制度です。
労働者や求職者が、資格取得までの費用をひとまず自己負担して、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講、修了した場合、資格取得費用の一部を助成金として支援してくれます。
教育訓練給付金制度を利用するための前提条件
そんなありがたい教育訓練給付金制度ですが、給付を受けるにはいくつか条件があります。ひとつずつ見ていきましょう。
雇用保険に加入して3年以上経過している
例外として、教育訓練給付金制度の利用が初めての人は、雇用保険に加入して1年以上経過していれば、助成金がもらえます。

前回の支給から3年以上が経過している
教育訓練給付制度の活用は、大型免許のみに留まらず、他の資格など様々あります。
そんな便利な教育訓練給付制度ですが、前回支給から3年以上が経過していないといけません。
離職から1年以内
退職時点で雇用保険に合計3年以上入っていて、かつ退職してから1年以上経っていなかったら、教育訓練給付制度は受け取れます。
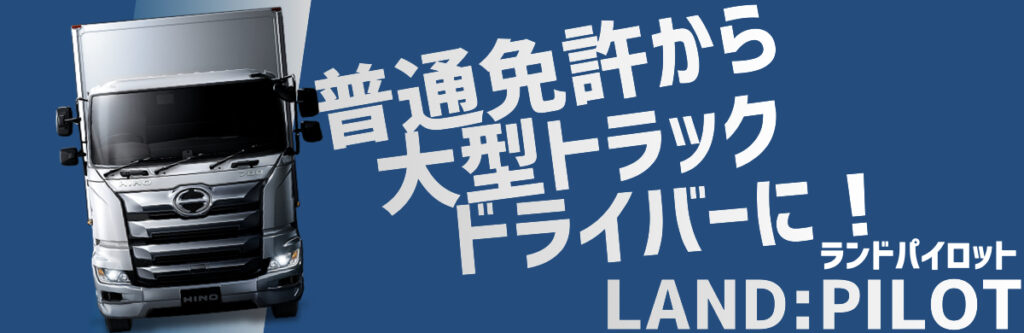
一般的な教育訓練給付金制度の流れ・活用する方法
支給資格の照会
まずは自分が、教育訓練給付金制度で助成金を受給資格があるのか、大型免許の教習1ヶ月前に近所のハローワークで確認しなければなりません。
実際に助成金の申請をするのは、費用をすべて支払った後です。
また助成金の支給対象となるには、国に定められた教習所に通う必要があります。
指定外の教習所で、大型トラックの免許取得を進めると助成金が支給されません。
入所の手続き
続いて、教育訓練給付制度で指定されている教習所への入校手続きをします。
教習所に入所する際は、教育訓練給付制度を利用することを伝えて、入校手続きをします。ここでの支払いの領収書は、必ず受け取り、大切に保存しておかなければなりません。
教習が終わってから、ハローワークで大型トラック免許の給付金申請手続きのとき領収書が必要となります。

講習の開始
大型免許取得を目標にひたすら努力するのみです。大型免許の教習にかかる費用は一旦自己負担し、あとで助成金を受け取る形になります。
受講時間は、持っている免許に応じて変わります。中型免許では15時間なのに対して、普通免許では30時間以上かかります
教習所を卒業する
おめでとうございます。教習所を卒業出来たら、教育訓練給付金支給申請書や教育訓練修了証明書を受け取ります。
万一、入所時に受け取った領収書がを失くしてしまっていたら、このタイミングで再発行してもらえます。
教育訓練給付金の申請手続き
大型免許の教習修了翌日から1ヶ月以内に、必要な書類がそろい次第ハローワークで給付金の申請を行いましょう。
1カ月を過ぎると、助成金の申請が無効になります。
必要な書類は、教習所で受け取った書類・領収書と、免許証といった本人確認書類、マイナンバー、雇用保険被保険者証または離職票があります。
さらに、助成金を受け取るために、通帳・キャッシュカードも持参しましょう。
教育訓練給付金の支給
助成金を申請すると、ハローワークの審査があります。
ハローワークの審査が終われば、ついに教育訓練給付金が届きます。
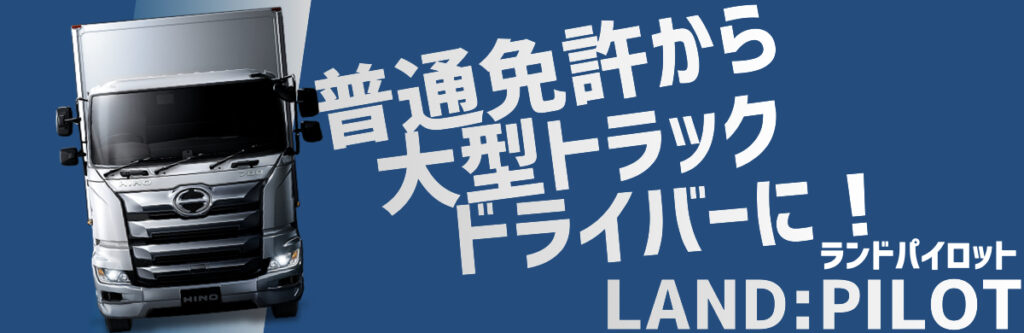
LAND:PILOTなら大型免許が無料で取れる!
LAND:PILOTは、無料で大型免許を取得でき、未経験・普通免許から最短10週間で大型トラックドライバーに転職できる、まったく新しいタイプのドライバー転職サービスです。
業界を熟知したキャリアアテンダントとの面談を経て、希望の転職先を決定、教習所での免許取得、入社先運送会社での実務研修(乗務含む)を経てプロの大型ドライバーとして乗務を開始できます。
まずは無料カウンセリングでキャリアアテンダントがあなたのドライバー適性を判定します!無料カウンセリングは以下のLINEから!

大型免許の難易度・合格率

大型免許を取りにくくさせている要因
まずは、何故大型トラック免許は取得が決して簡単ではないのか。その原因を紹介していきたいと思います。
普通免許より取得に時間がかかる
大型免許は、数ある運転免許の中で決して簡単に取れる免許ではなく、高度なドライビング・テクニックが必要です。
それゆえ普通自動車免許より、取得までに比較的時間がかかってしまいます。時間の大半は、ドライビング・テクニックの向上のための教習に当てられます。
取得までの費用が安くない
大型免許は、決められた教習時間をやりきらなければなりません。
教習時間が長いので、それに伴って費用もかさんでしまいます。
普通車より高度な運転技術が必要とされる
大型車は、普通自動車よりはるかに大きく重いです。
それゆえ、普通自動車を運転するときとはわけが違く、大量の荷物を運んでいるトラックが事故を起こしてしまうと、大きな被害をもたらしてしまうかもしれないので、ドライバーは十分に注意しなければなりません。
ミラーでは見えない死角がある

大型トラックはミラーで見える部分が狭く、死角も大きいです。
慣れるまでは大変ですが、もし慣れないという時は、バックモニターを使ってやるとかなり簡単になります。会社によってはバックモニターが備え付けてある所もあるので、確認してみて下さい。
エアブレーキの感覚を掴むまでが大変
大型車にまだ慣れていない人が難しく感じるのがエアブレーキです。
普通自動車よりはるかに重い大型車は、ブレーキが強くかかってしまうので、普段通りにブレーキを踏むと急停止してしまいます。ゆっくりと踏むのがポイントです。
カーブするにはポイントがある
大型車はサイズの大きさに伴い内輪差が大きいので、カーブは気を付けないと車体をぶつけてしまいます。車体の感覚に慣れるまではミラーをよく見ながらカーブしていきましょう。
オーバーハング部分の長さ
オーバーハング部分は、後輪の後方部分です。大型車はこのオーバーハング部分が長いので、ちょっとした運転操作のミスで、曲がるときに事故が起こりかねません。
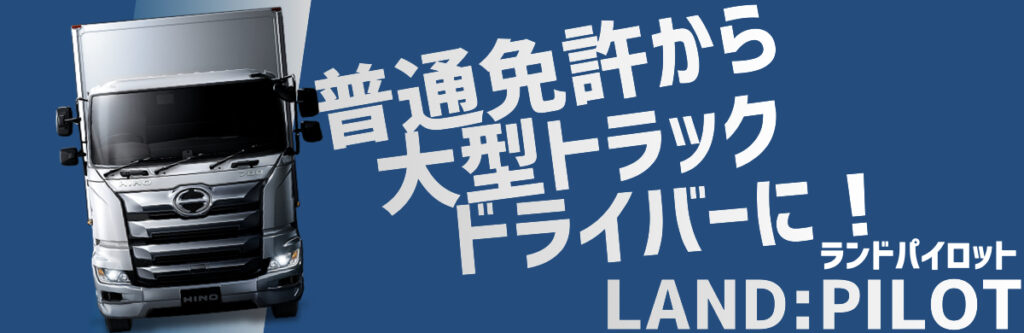
大型免許の合格率の変遷
2007年の道交法改正以降、大型免許の合格率は増加しています。
平成23年・・・88.9%
平成24年・・・88.8%
平成25年・・・90.3%
平成26年・・・91.0%
平成27年・・・91.4%
平均合格率は9割を超えてますが、一発試験の合格率は平均30%を切っています。
大型免許取得の心得

運転が難しい大型トラックですが、もちろんコツもあります。3つの心得を紹介します。
心得1.カーブ
運転の基本、カーブ。基本といえども、慣れないと難しいと感じる人も決して少なくないです。カーブの心得は、ひとつに周りの確認です。人、障害物の確認をしましょう。
大型車は内輪差が大きいですが、ハンドルを大きく切ると、それに伴い内輪差も大きくなります。さらに、速度を出しながらカーブすると荷台に引っ張られて横転してしまうかもしれません。カーブするときは、ゆっくり・慎重にハンドルを切りましょう。
心得2.左折時
左折時は、内輪差に注意してカーブする必要があります。巻き込み事故は大型トラックの事故あるあるです。右折と違って、自分の目で確認することができないので、サイドミラーを利用しつつ後輪確認してハンドルを切りましょう。
ハンドルを切るタイミングは、左折する道路を超えたところが基本です。トラックの速度が出ているほど、ハンドルのスピードも速くないといけないので、ゆっくり左折することを心がけましょう。
心得3.後方感覚
後方感覚は大型免許の試験で試されます。2回チャンスがあり、後方のポールを目印にバックし、そのポールとの距離を50cm以内に収めれば合格、50cmに収められなければ減点、当たれば不合格です。
心得は、荷台の後ろの端を見つつポールとの距離を見る方法がおすすめです。サイドミラーより結局は、自分の目が確実です。
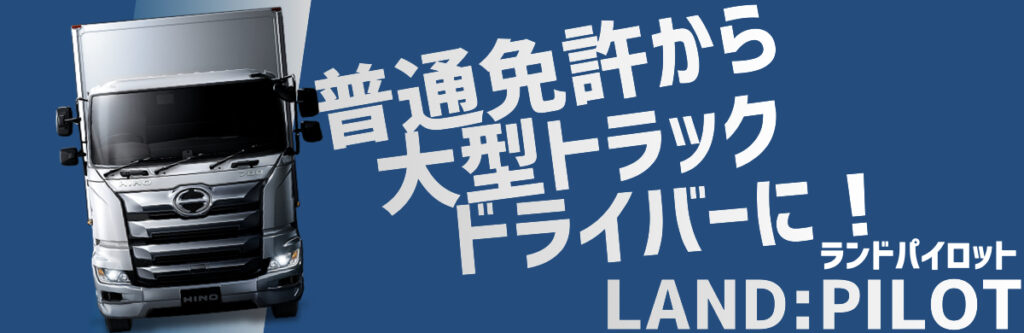
未経験・普通免許からの大型トラックドライバー転職サービス
「LAND:PILOT(ランドパイロット)」
大型取得サポートだけじゃない!あなたに最適な就職先を一緒に探します
- 東証一部上場企業等 大手求人多数
- チャーター便・幹線輸送便・地場ルート便など職種ラインナップ多数
- 希望給与・年間休日数・勤務体系から条件にあった企業を探せる!







